このようなお客様に選ばれています






こんなお悩みありませんか?

社内でBIM担当が一人で孤軍奮闘している

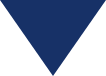

BIMworkにいつでも相談できる!

干渉チェックが形骸化し、施工段階で手戻りが頻発

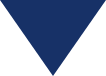

BIMworkならモデルを活用して干渉チェックをお任せ

テンプレ/ファミリが乱立し、モデル品質がバラバラ

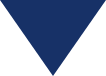

BIMworkならプロジェクトのモデルチェックも対応可能!

Revit・Dynamoを使いこなせる人材が定着しない

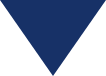

BIMworkでDynamo・アドイン開発も対応!
BIMworkなら
解決できます!
BIMworkの特長
01
意匠・構造・設備 設計BIMワンモデル
統合BIMモデルサービスは、意匠設計、構造設計、設備設計のすべてのニーズに対応し、プロジェクト全体の効率と精度を向上させる包括的なソリューションです。各分野の専門性を活かし、建築プロジェクト全体の効率性と精度が向上し、設計・施工プロセスがスムーズに進行します。


02
BIMデータ活用
私たちのBIMデータ活用サービスは、建築プロジェクトの全体を通じてBIMデータを最大限に活用するためのソリューションを提供します。データの一元管理・プロジェクトの可視化・意思決定の迅速化などのメリットを提供します。
03
パース作成と3Dプリンター活用など 副次的なBIMのメリット
BIMは、建築設計と施工の効率化にとどまらず、多くの副次的なメリットを提供します。パース作成や3Dプリンターを利用しての模型作成、3Dアニメーション作成などもBIMworkにご依頼いただけます。

BIMworkの優位性
| 自社でBIMに 取り組む | 派遣社員を入れて BIMに取り組む | 優位性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初期コスト | ソフト購入・教育費が高額 | 教育費は小だが派遣契約費が必要 |  外注費のみで導入可 | ソフト購入不要。プロジェクト単位の外注費のみで初期投資を最小化。 |
| 運用コスト | 人件費は固定だが内部化で平準化 | 長期派遣は高コスト化 | 案件単位で変動し人件費固定なし | 社員と異なり固定費とならず、プロジェクトごとにコストを検討できます。 継続的な教育やサポートはBIMwork内で行っており、発注者側の運用コストを低く抑えることができます。 |
| 導入スピード | 社内体制づくりに準備と教育が必要 |  即戦力をすぐ投入できる |  発注後すぐ着手可能 | 受注後すぐに専任チームをアサインし、即スタートが可能。 |
| 専門性 | 自社育成が必要 |  専門スキルを持つ人材を確保 |  BIMマネージャ主導で最適化 | 豊富な経験を持ったチームが対応するため、より高品質なサービスを提供できます。 |
| 作業効率 |  標準化が進めば高効率 | 個人の習熟度に依存 | 多様案件で調整可だが指示必須 | プロジェクト専任のBIMマネージャーが効率的な作業の割り振りを行うため、効率的にプロジェクトを進行できます。 |
| 品質管理 |  自社基準を整備すれば可 | 派遣でも運用ルール次第 | 幅広い会社を見てきた 豊富な経験で対応 | 高い品質管理基準に基づいて作業を行うため、プロジェクトの品質を保証できます。 |
| 設計の整合性 |  部門連携が鍵 | 人材が分散すると調整負荷 |  意匠・構造・設備が統合された モデルの提供 | 設計三分野統合されたBIMモデルを提供することで、プロジェクト全体の一貫性を確保します。 |
| カスタマイズ対応 |  自社開発やアドイン導入自在 | 派遣範囲外は対応困難で人の入れ替えが必要 |  追加要件に応じ別途開発可 | Dynamo・アドインともに顧客の特定のニーズや要件に応じた作成が可能です。 |
| 技術サポート | 社内リソースで限定的 | 派遣社員の契約に依存 |  専任チームによるサポートや BIMコンサルタントとの連携 | 専門的な技術サポートを提供し、クライアントのニーズに迅速に対応します。 |
サービスプラン
ベーシック
¥350,000 / 月
(税別)
- 月 2回 オンライン / 月 1日対面
- スタッフ集合研修
- モデル監査レポート
- チャット相談 無制限
スタンダード
¥500,000 / 月
(税別)
- 週1日 対面
- Dynamo開発(月1~2個)
- BIM標準・テンプレ整備
+ 前項の全て
プレミアム
¥800,000 / 月
(税別)
- 週2日 常駐サポート
- Revitアドイン開発
- BIM関連ミーティング参加
+ 前項の全て
期待できる成果
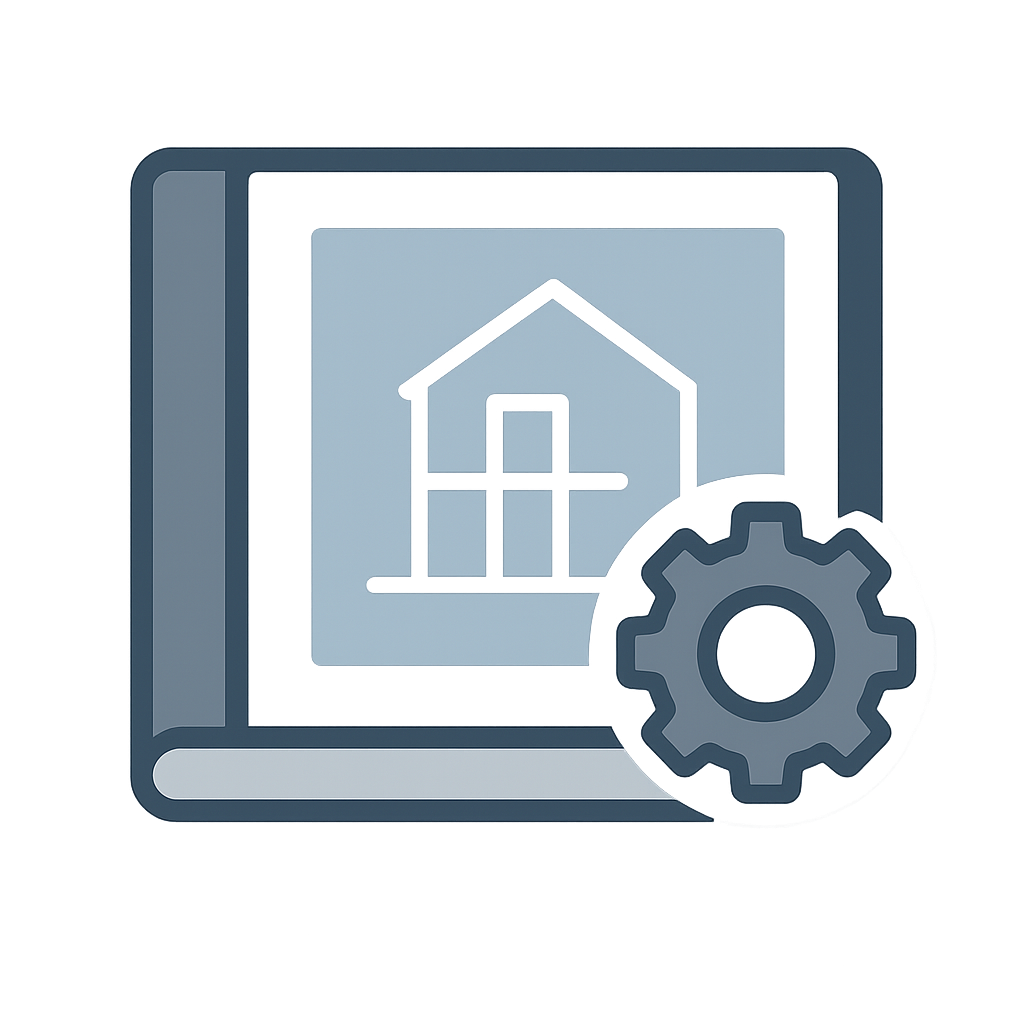
BIM運用ガイドライン / テンプレート一式
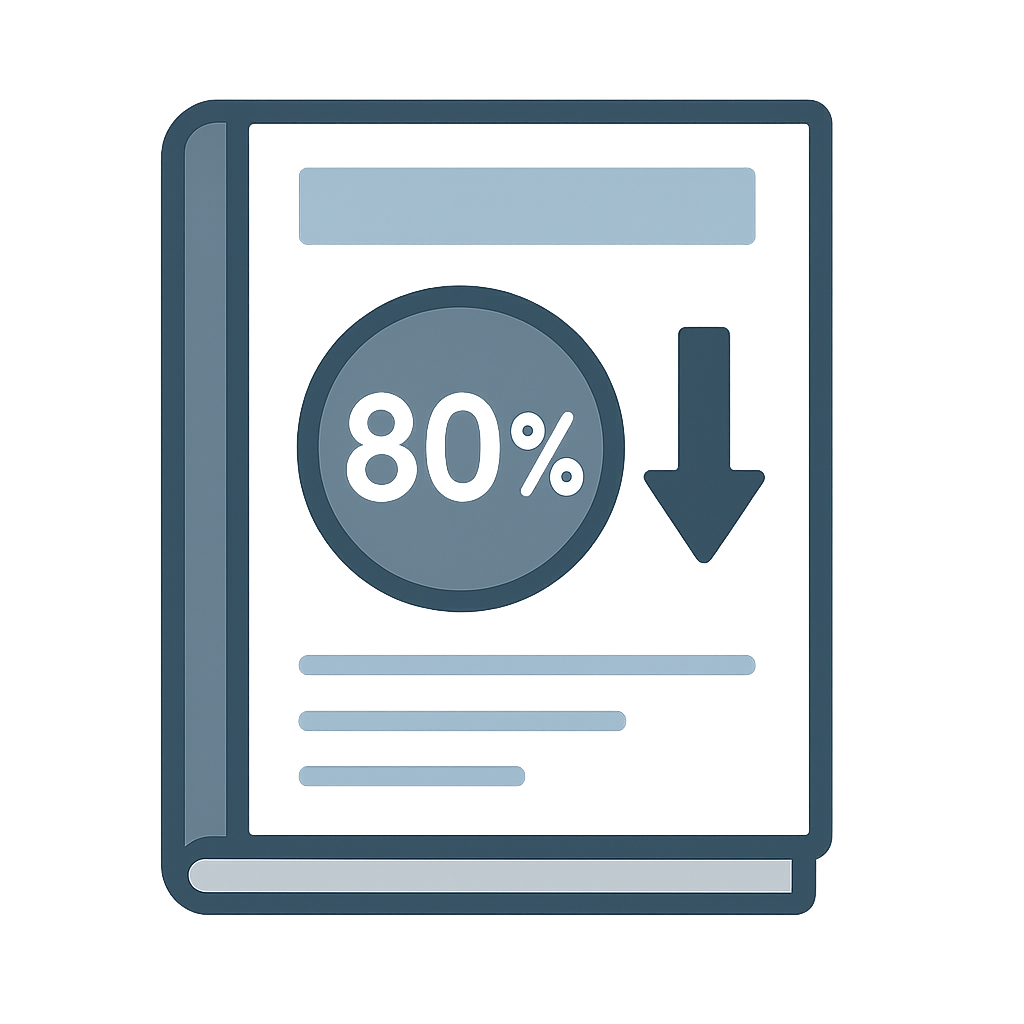
干渉指摘80%削減レポート

スタッフ技術力評価表 & 研修プラン
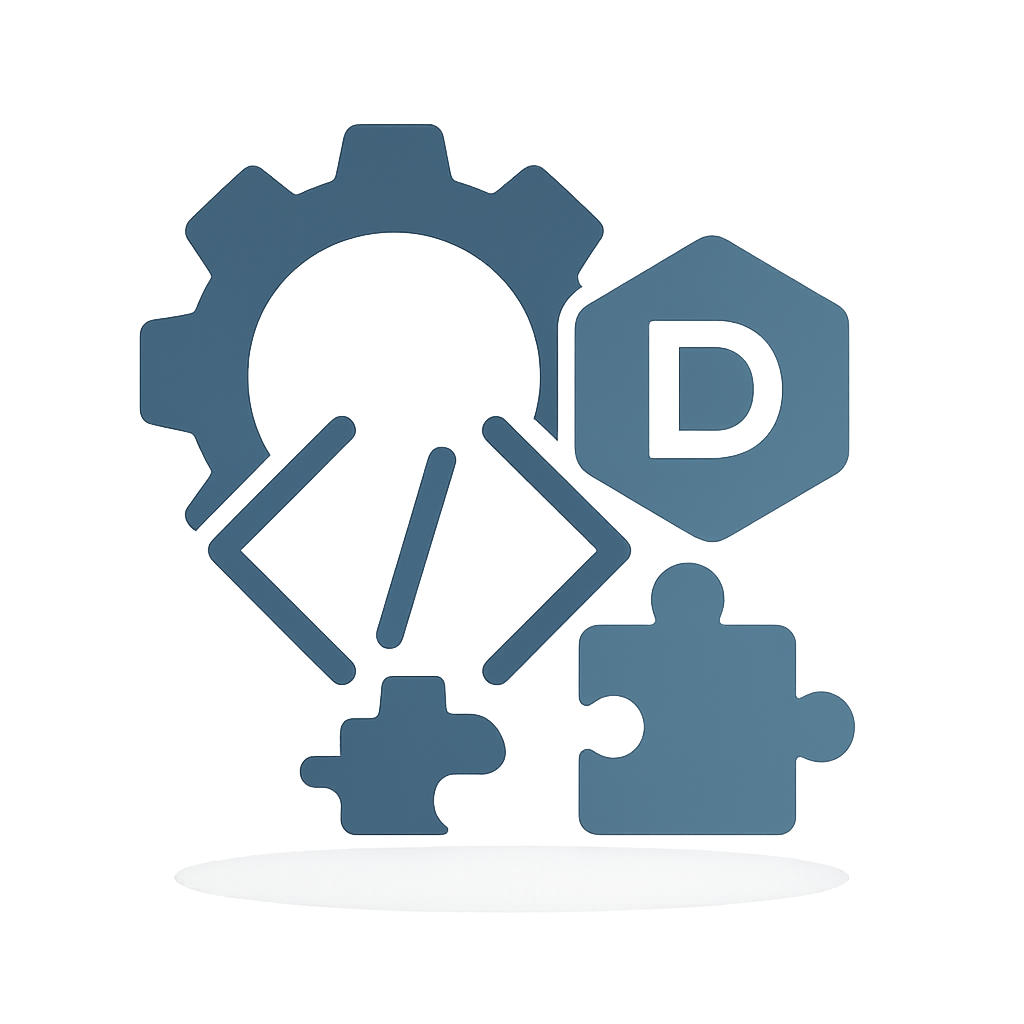
自動化Dynamoスクリプト / アドイン
まずは無料のご相談を
導入実例
BIMworkをご利用いただいているお客様の実例をYoutubeにて公開しております。
カスタマー1
こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。
カスタマー2
こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。
カスタマー3
こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。こちらにコメントが入ります。
よくあるご質問
-
BIMworkを利用することでどのようなメリットがありますか?
-
私たちのサービスを利用することで、設計の一貫性と精度が向上し、プロジェクト全体の効率が高まります。
意匠設計、構造設計、設備設計のBIMモデルを統合することで、設計ミスの減少、不要なコミュニケーションコストの削減、スムーズなプロジェクト進行に貢献します。
-
プロジェクトのモデル作成、作図の料金体系はどのようになっていますか?
-
費用はプロジェクトの規模や要件に応じて異なります。詳細な見積もりは、お客様のプロジェクト情報をもとに個別に算出いたします。まずはお気軽にご相談ください。
-
BIMコンサルティングの契約期間の縛りはありますか?
-
最低3ヶ月からお願いしています。初月はトライアル価格25万円です。
-
意匠と構造だけ、あるいは構造と設備だけなどで依頼できますか?
-
はい、可能です。まずはお気軽にご相談ください。
-
ソフトウェアは何に対応していますか?
-
意匠・構造はRevitを、設備はRebro/Revitを使用しています。
Navisworks、Dynamo、BIM360など主要BIMツールに対応しています。
-
オンラインのみでも成果は出ますか?
-
多くのクライアントがオンライン中心で成果を出していますが、必要に応じて現地訪問も行います。
-
BIMモデルの品質管理はどのように行いますか?
-
高品質なBIMモデルを提供するために、BIMworkからBIMマネージャーをプロジェクトに任命し、品質管理を行います。
レビュー、綿密なチェックリスト、継続的なフィードバックサイクルを通じて、品質を向上します。
ご依頼から納品までの流れ
お見積り依頼
STEP01

お見積もりフォームよりご依頼。
訪問打合せ
STEP02
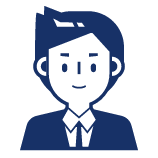
ご希望の日時にご訪問させて頂きます。
ヒアリング
STEP03
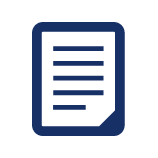
プロジェクトの課題、規模、難易度などヒアリング。
お見積り
STEP04
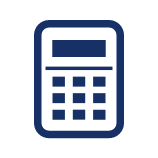
ヒアリング内容を基に見積書を作成。
ご契約
STEP05
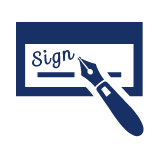
契約書を取り交わしご契約となります。(精算の時期などもお客様にあわせてこの時に決定)
キックオフミーティング
STEP06
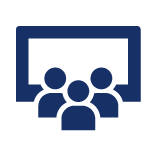
キックオフミーティングを開催し、プロジェクト始動です。
BIM定例会議
STEP07

プロジェクト中はBIM定例会議開催し、進捗の確認も行います。
プロジェクト終了
STEP08

客先納品完了となればプロジェクト終了です。
まずは無料のご相談を
アライアンス企業募集
アライアンスに加入してくださる企業様を募集しております
私たちは、意匠設計・構造設計・設備設計のRevitモデルを一括で作成する新しいサービスを提供するにあたり、ともにBIMモデルを作成していただける優秀なパートナー企業を募集しております。
弊社のサービスは、建築プロジェクト全体の効率と品質を向上させることを目指し、意匠設計、構造設計、設備設計のすべての分野において高品質なBIMモデルを提供します。これにより、設計の一貫性、精度、コスト管理、リスク管理が飛躍的に向上します。
募集要項
募集対象
- 意匠設計BIMモデルの作成に経験と実績を有する企業
- 設備設計BIMモデルの作成に熟練した企業
応募条件
- Revitの使用経験(目安3年以上)
- 建築プロジェクトにおけるBIMでのモデル作成・作図の実績
- 迅速かつ正確な作業能力
- 柔軟な対応力と協力姿勢
パートナー企業としてのメリット
- 大規模プロジェクトへの参画機会
- 共同でのマーケティングおよびプロモーション活動
- 最新のBIM技術およびトレンドへのアクセス
- 長期的なパートナーシップの構築
- 安定した業務受注と持続的な成長の機会
応募方法
興味をお持ちいただける企業様は、以下の情報を含む応募書類を弊社までご送付ください。
- 会社概要および実績
- BIMソフトウェアの使用経験および保有スキル
- これまでのプロジェクト事例
- 連絡先情報
連絡先
mizutani@mthreestars.com
件名:BIMモデル作成パートナー企業応募
アライアンス加入についてのご相談は下記へお電話ください
(代表直通)
(代表直通)
アライアンス企業募集






アライアンス加盟までの流れ
加入のご相談
STEP01
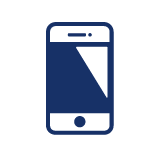
まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。
ZOOM面談
STEP02

まずはZOOMでカジュアル面談。(BIMworkアライアンスについて説明します)
ヒアリング
STEP03
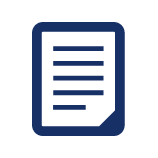
説明を聞いたうえで加入の意思が固まれば、後日再度面談。(これまでの実績や経験をヒアリング)
弊社にて検討
STEP04

弊社内で検討させていただきます。
加入決定
STEP05

検討の結果、加入となりましたらご連絡差し上げます。
守秘義務契約締結
STEP06
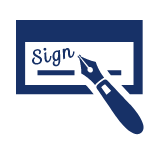
守秘義務契約締結 、 BIMアライアンスチャットグループ(chatwork)加入 、BooT.oneアドイン1ライセンス支給
プロジェクトのお見積り
STEP07
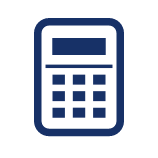
クライアントからプロジェクトの依頼が来た際に、お見積もり頂きます
プロジェクトに参画
STEP08

発注が決まればプロジェクトに参画となります。
運営会社概要

| 商号 | エムスリースターズ株式会社 |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役 水谷 亮介 |
| 事業内容 | 構造BIMモデル作成 および 構造図作図業務 |
| 設立 | 2019年 4月16日 |
| 所在地 | 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1丁目8-4 |
| 郵便物送付先 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-13-12-E205 |
| 資本金 | 500万円 |
| WEB | https://www.mthreestars.com/ |
